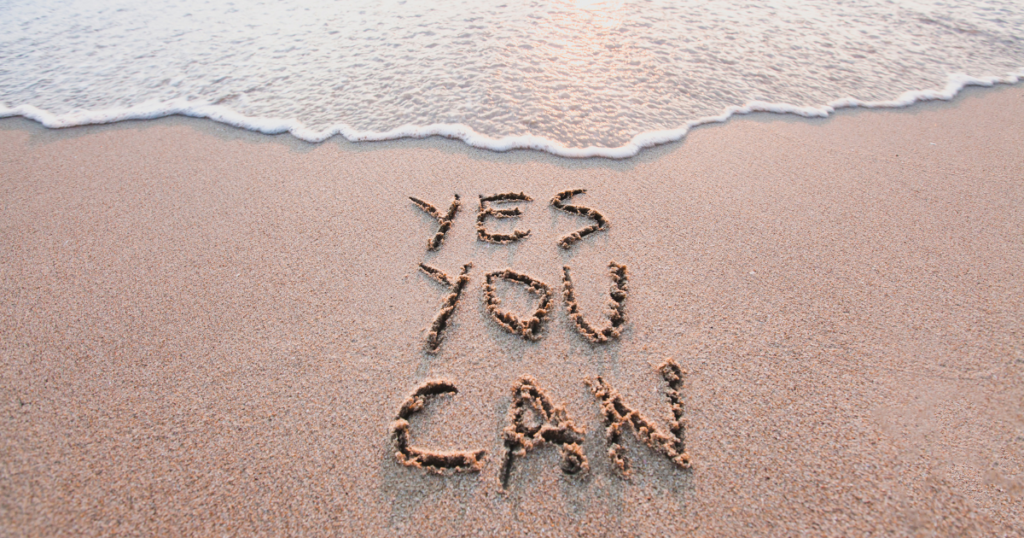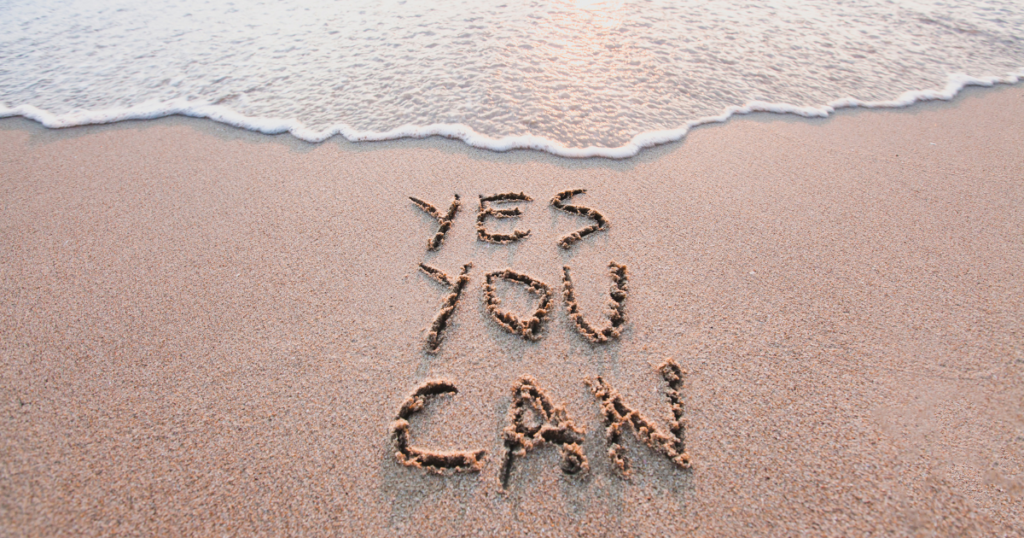kaco
kaco今回、思わぬお誘いによって、私は雅楽に初挑戦することに。
雅楽とは
雅楽は日本に伝わる伝統音楽の中で最も古い音楽。神社の境内などで耳にする、ゆったりとした高音の音色。特徴ある音とリズムが印象的な音楽。今から1400年前、仏教と共に日本に伝わったと言われています。
神仏を崇拝する私にとって、雅楽の音色は私の中では神の音。
まさか自分がその音を奏でられるチャンスがやってきたなんて・・・。
夢のような話に、少し興奮氣味のスタートでした。



正直、雅楽について無知な私。まずは知ることからはじめないと。
雅楽の中心的な役割である管楽器、その代表的なものが笙、篳篥、龍笛。
雅楽を織り成す楽器たちのこと
★ 笙(しょう)
鳳凰が翼を立てている姿と言われる笙。複数の音を同時に出せるため、和音を奏でるのが主で、他の楽器の音を包み込むような役割があります。その音色は天から差し込む光の音を表すとされています。
★ 篳篥(ひちりき)
漆を塗った竹で作られ、表側に7つと裏側に2つの穴をもつ縦笛。笙に比べると簡単に演奏できるように見えるが、音程が不安定なため、演奏するのは非常に難しく技術が必要。その音色は人の声つまり地上の音と表すとされています。
★ 龍笛(りゅうてき)
7つの指穴がある横笛で、2オクターブの音域を持っています。龍笛という名の通り、天と地の間を行き交う龍の鳴き声を表しているとされています。天と地の間の空間を象徴しているそうです。
雅楽では笙、篳篥、龍笛を合奏することが基本の表現となり、それは「天」「地」「空」を合わせる、つまり音楽表現がそのまま宇宙を創ることと考えられているのです。


調べないかぎり知り得なかったこと
私にできるんだろうか・・・という不安と、やってみたい!というワクワクが入り混じって、心の中がちょっぴりザワザワしていたけど、知れば知るほど興味が湧いてくる雅楽。
そんなとき、ふと思ったんです。
毎朝参拝のとき「私にできることがあれば、何でも言ってください」と言っていたので、これはもしかして、神様に与えられたことなのかもしれないって・・・。
そう思った瞬間、わたしはできる!という想いに変わり、やる氣がみなぎってきたんです。
聞けば、雅楽の世界でも高齢化が進み、継承の課題があるそうです。
そんな大切な日本の文化、お祭りの音色を未来へつなぐために、今の私にできることをやってみよう、と心に決めたんです。
今回私は、難しいとされる篳篥にチャレンジします!


篳篥は、小さな楽器なのに音量が大きく、ひときわ存在感を放つ楽器。
目立ちたがり屋の私にはぴったり!?・・・だけど、間違えるとこれまたバッチリ目立つ(笑)
音を出すだけでも難しく、同じ指使いでも違う音が出るという不思議な特徴もあって、音程がとても不安定なのも、篳篥ならでは。
難しいからこそ、面白い!だからこそ、やりがいがある!
今現在、なんとか音は出るようになってきたけれど、毎回音にばらつきがあって、本当に奥が深いなぁと思います。
5月のお祭りに向けて、楽しみながらがんばります!!